森の端っこに小さな家があった。お父さんは樵、お母さんは畑をやっていて、カリス坊やはいつも、裏の森で一人で遊んでいた。 ある日、カリス坊やは坊やの背丈の半分もない、小さな木を見つけた。木という木は、いつもいつも全部、坊やよりずっと大きかったから、坊やはとてもびっくりした。
けれども、もっとびっくりしたのは、そんなに小さかった木が十日後、カリス坊やと同じくらいの背丈になっていたことだった。
びっくりしているカリス坊やの所へ、森の泉の妖精ライ・ラヴァーはやって来た。
「びっくりしたかい、坊や」
そう言って、妖精はくすりと笑った。
「でもね、これはもっともっと大きくなるんだよ。どんどん大きくなる、これは、塔なんだから」
「うそだぁ」と、カリス坊やは応えた。「だって、これは木じゃないか」
ライ・ラヴァーはくすくす笑う。
「そうだよ、木だ。だから、塔なんだよ。見せてあげよう。ほら」 たちまちに、辺りは木の壁になった。
いや、違う。
塔の中になった。真ん中に、螺旋階段がぐるぐると上へ延びていた。
「ほら、そいつが木の中だ」
ライ・ラヴァーの声が何処からともなく言った。
カリス坊やは螺旋階段のてっぺんを見上げた。きらきらと輝く、宝石のようなお陽さまが見えた。
その、とてもきれいで、とても不思議に輝くお陽さまの所へ、坊やはどうしても行きたくなった。それで、お陽さまに向かって延びる螺旋階段の一段目に登った。
「これを登っていったら、あのお陽さまの所へ行けるかな」と、カリス坊やはきいた。
「さあ、どうだろうね」と、姿の見えないライ・ラヴァーは答えた。
そして反対に、坊やに訊ねた。
「“バベルの塔”ってのを、知っているかい?」
「知らない」
階段を上りながら、坊やは答えた。また、ライ・ラヴァーは笑った。
「昔、王様が居てね……」
ライ・ラヴァーが話しだした時、カリス坊やの足元に、緑の三角帽子の小人が走っていった。
「ねえ、どこへ行くの」と、坊やはきいた。
小人は走りながら「どこって、この上さ。ずっと登って行って、お陽さままで行くのさ」と答えて、そのまま走って行ってしまった。
「その王様は、空の上の神さまの所へ行きたいと思ったんだ」と、素知らぬ声で、ライ・ラヴァーは続けた。
ライ・ラヴァーの声を聞きながら登って行くカリス坊やの横を、さっきのと同じ恰好の小人が大工道具を持って走っていった。
「ねえ、どこへ行くの」と、坊やはきいた。
小人は走りながら「どこって、この上さ。この塔を、上へ上へ延ばして積み上げて、お陽さままで行くのさ」と答えて、そのまま走って行ってしまった。
「それで王様は、神さまの所へ登る、高い高い塔を造ろうとしたんだよ」と、やっぱり素知らぬ声で、ライ・ラヴァーは言った。
お陽さまを目指して登って行くカリス坊やの後ろから前へ、緑の三角帽子の小人が百人くらい、いっぺんに走っていった。
「ねえ、どこへ行くの」と、坊やはきいた。
小人たちは走りながら「どこって、この上さ。塔がもうじき出来るんだ。塔を登って、お陽さままで行くのさ」と答えて、そのまま走って行ってしまった。
「その塔はね、あとほんの少しの所までは出来たんだ。だけどね……」と、ライ・ラヴァーは続けて言った。 どんどんと螺旋階段を登るその先で、たくさんの小人がなにか大騒ぎをしていた。
「ねえ、どうしたの」と、坊やはきいた。
「言葉がわからなくなった!」と、小人の一人が言った。「工事ができない。塔ができない」「だけど、もう少しでお陽さまだ」
別の小人が言った。「だからいっきに走って登ろう」
小人の中の何人かが走りだした。カリス坊やも一緒に走りだした。
「だけどね、神さまがお怒りになって、皆の言葉がわからないようにしておしまいになったのさ」と、ライ・ラヴァーは言った。 だけど小人たちと一緒に走って上るカリス坊やは、もうライ・ラヴァーの声なんか聞いていない。
いつの間にか、小人たちの帽子は緑から、赤や黄色や茶色に変わっている。
「ねえ、あとどれだけ走るの」と、坊やは息をはあはあ言わせながらきいた。
小人たちもはあはあ言いながら「あとちょっとだ」と答えて、そのまま走りつづけた。
そして本当にあと少しで、お陽さまに手が届きそうなくらいになった。
「やった」と叫んで、坊やは手を延ばした。 そのとき。
パキン、と、音がした。
ガラン、と、音を立て、
ドーン、と、音がした。
小人がぱらぱら落ちて行く。坊やも落ちる。
木の螺旋階段が枯れている!
ライ・ラヴァーのくすくす笑いが聞こえて、「バベルの塔はそれから、神さまに崩されてしまったんだよ」と言った。
「でも、これは木じゃないか」と、まっさかさまに落っこちながら、カリス坊やは叫んだ。
ライ・ラヴァーは笑う。
「そうだよ。だから、枯れて、腐ってしまうのさ」
カリス坊やはそのまま地面に落っこちた。
「おやおや。人の話を聞かないからさね」と、ライ・ラヴァーは言った。
そして、倒れている坊やの回りをくるりと飛んで、そのまま泉へ帰っていった。
坊やの横には、腐った木が一本、立っていた。
――――それは、森の泉の妖精“嘘の恋人”の、いつか語った物語。
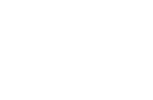

コメント、感想など頂けると嬉しいです